オペラ『ルル』演奏会の批評
![]() ザ・フルート(2005年9月/10月号77)
ザ・フルート(2005年9月/10月号77)
 |
 |
クーラウへの認識を新たにさせる充実のステージ
オペラ『ルル』
クーラウのオペラ《ルル》が上演された。作曲家の故国デンマーク・コペンハーゲンの王立劇場で1838年に上演されて以来、実に167年ぶりの壮挙。台本がデンマーク語であることなどから長らく陽の目を見ることのなかったこの作品に再び生命を宿したのは、この日タクトを執ったフルーティスト石原利矩の情熱だ。自身のリサイタルで演奏するためクーラウの研究を始めた石原が《ルル》と出逢ったことは、作品にとっても幸運だった。主人公ルルが人を惑わす笛の音を駆使して活躍するこのオペラの作曲に、「フルートのベートーベン」といわれるほどの多くのフルート作品を遺したクーラウが集大成の意気込みで臨んだことは大いに想像でき、その真価を世に問うことは、やはりフルートという楽器とこの作曲家への深い理解と愛情なくしては成し得なかっただろうと思われるからだ。
物語は「とらわれの王女を悪役から助け出す王子」というおとぎ話。モーツァルトの《魔笛》と同じ題材だが、《魔笛》よりも原作に忠実な内容になっている。手追いの虎を追って妖精ペリフェリーメの森に入り込んだ王子ルルは、そこで出会った妖精の娘シディの幼友達ヴェラから、シディが魔法使いディルフェングに捕らわれている話を聞く。シディが自分と魂で結ばれた相手だと信じたルルは彼女の救出を決意、ペリフェリーメから渡された魔法の指輪と魔法の笛を手にディルフェングに立ち向かう。
台本はわかりやすくするため日本語訳を用いた。タイトルロールを演じた福井敬は、使命感に燃える果敢な若者を熱く演じた。彼の明快な日本語歌唱は、観客を作品の世界へ引き込むのに成功した大きな要因のひとつだろう。ディルフェングの息子バルカの久岡昇は、とぼけたキャラクターを存分に発揮して楽しい。ペリフェリーメに起用された女優の夏木マリの存在感はさすがで、童話的な舞台で効果的なアクセントとなった。ディルフェングや魔女たちを惑わせる笛の音は、フルートを知り尽くしたクーラウの本領を思わせる。演じたのはデンマーク放送交響楽団の主席フルーティスト、トーケ・ルン・クリスチャンセン。長年にわたってクーラウのフルート作品に取り組んでいるだけあって、大変印象深く幻惑的な音色だ。全3幕で3時間を超える大作だが、この作曲家に対する認識を新たにさせられる、充実した内容だった。(荒井幸太)
-「ザ・フルート」9/10月-77号(2005)ページ
![]() 音楽の友(2005年8月号)掲載記事
音楽の友(2005年8月号)掲載記事
 |
2つのオペラの日本初演
この6月、2つの重要な「日本初演」があった。1つはクーラウ作曲の《ルル》。1824年に初演された「もう一つの魔笛」とも言われるオペラだ。そしてプッチーニの未完のオペラ《トゥーランドット》をL・ベリオが補筆完成したもの。こちらは、普段聴きなれている版とは違ったグランドフィナーレが、日本で初めて鳴り響いた。
クーラウ《ルル》、
ベリオ補完版プッチーニ《トゥーランドット》
もう一つの《魔笛》、167年ぶりに東京で蘇る
---------クーラウの《ルル》
取材・文:田辺秀樹
写真:浦野俊之
オペラ《ルル》といってもアルバン・ベルクの《ルル》ではない。作曲家フリードリヒ・クーラウ(1786~1832)。ドイツに生まれ、デンマークに移住して活躍した作曲家で、ピアノ学習者は「ソナチネ」でお馴染みだろう。1824年コペンハーゲンで初演された《ルル》は、クーラウのオペラの代表作。物語はドイツ18世紀の作家ヴィーラントの魔法メルヘンに基づくもので、その点で共通するモーツァルト作曲の《魔笛》と相当似ている。光の妖精ペリフェリーメと邪悪な魔法使いディルフェングの対立を軸に、旅する王子ルルが王女シディをディルフェングのもとから救い出すと言うストーリーは《魔笛》そっくりだが、善と悪がはっきりしている点で、《魔笛》よりもすっきりしているといえる。
今回の舞台上演は、1838年以降世界中で上演が途絶えていたこのオペラを、167年ぶりに日本で再演したもの。国際フリードリヒ・クーラウ協会理事長でこの上演の指揮を務めた石原利矩氏の驚くべき情熱と実行力の輝かしい成果だ。福井敬、澤畑恵美、高橋薫子、久岡昇、松本進らの歌手陣は、みな歌も演技もすばらしく、夏木マリは語り役ペリフェリーメでさすがと思わせる存在感を示した。日本語訳詞が聞き取りやすかったことも特筆されよう。会場の東京文化会館大ホールは満員の盛況。これぞまさに快挙である。日本で甦ったこの「もう一つの魔笛」のさらなる本格的復活のためにも、再演が遠からず行われることを願ってやまない。(6月4日)
 |
「音楽の友」8月号(2005) 34~35ページ
![]() 音楽現代(2005年8月号)掲載記事
音楽現代(2005年8月号)掲載記事
 |
クーラウ/歌劇「ルル」
181年ぶりの蘇演の快挙
デンマークの作曲家クーラウが1824年に発表したオペラ「ルル」は初演以来忘れ去られてしまい、演奏会形式を別にするとこれがなんと181年ぶりの蘇演だという。それが国際フリードリヒ・クーラウ協会の主催により日本のスタッフ、キャストにより上演されたのは快挙といってよいだろう。快挙といったのは、これが単なる試演ではなく、本格的な上演として立派な成果をあげていたからである。
「ルル」といっても、ベルクの同名のオペラとは何の関係もない。モーツァルトの「魔笛」と同じヴィーラントの原作で、「魔笛」のタミーノに相当する役名がルルという名前であることにタイトルは由来している。「魔笛」ではフリーメイソンの思想の影響が大きく、夜の女王(ここではペリフェリーメ)とザラストロ(ここではディルフェング)の善役、悪役の立場が途中で逆転するなど複雑な人物関係があったが、「ルル」ではそのようなことはない。
ストーリーは基本的には「魔笛」と同じで、邪悪なディルフェング(松本進)に娘シディ(澤畑恵美)を攫われた光の精である母親ペリフェリーメがその救出を旅の王子ルル(福井敬)に託し、老人に変装して魔法使いの城に侵入した彼は見事に目的を達成してめでたくシディと結ばれ、一方ディルフェングは地獄に落ちる、という内容である。ルルが虎に襲われながら登場したり、モノスタートスに相当するバルカ(久岡昇)などの役柄も、「魔笛」を知っている人にはすぐにその意味が分かるが、パパゲーノの性格はルルが兼ねているようだ。
第2幕ではバロック・オペラ風のバレエの挿入がオペラを冗長に感じさせたとはいうものの、具象かつ無駄のない演出(十川稔)はこのような珍しい作品の場合きわめて有効だった。ただし母親の語り役にタレントの夏木マリが起用されたのは、台詞の巧拙は別にして周りの出演者との違和感が残るが、日本語訳詞上演はジングシュピールとして台詞が多い作品なので肯定的に受け止めておきたい。
歌手陣の水準も高く、石原利矩の指揮は作品に対する丁寧なアプローチが好ましい。それだけにこれがただ一回の公演というのは惜しまれる。管弦楽は東京ニューシティ管。(6月4日、東京文化会館)(野崎正俊)
 |
-音楽現代」8月号(2005) 28~29ページ
![]() ショパン(2005年8月号)掲載記事
ショパン(2005年8月号)掲載記事
 |
 |
『魔笛』よりも・・魔的
オペラ『ルル』
道下京子
デンマークの作曲家フリードリヒ・クーラウのオペラ『ルル』の初演は1824年。近年、演奏会形式では数回演奏されているものの、本格的なオペラとしての上演は、この東京での上演が実に168年ぶりとなるそうだ。この貴重なオペラ公演に、多くの聴衆が訪れ、会場はほぼ満席状態であった。指揮は、インターナショナル・フリードリヒ・クーラウ協会理事長の石原利矩、管弦楽はニューシティ管弦楽団。ギュンテルベアの台本を日本語訳したものが使用された。ルル役の福井敬、シディ役の澤畑恵美、ヴェラ役の高橋薫子など、この舞台で、日本の声楽界の精鋭たちにめぐり会えたことは、実に幸運であった。彼らの充実した歌唱力は、この作品を世に再認識させ昇華させるに充分であった。そして注目すべきはバルカ役の久岡昇、ディルフェング役の松本進、そして羊飼い役の青地英幸の演技力である。デンマークのメルヘンの世界を、親しみやすく表現しており、オペラが「聴く」だけでなく「観せる」ものであるということを、改めて知らしめてくれた。その反面、前記以外のキャストや合唱について、演技面で表現がともなっておらず、その点は惜しまれる。クーラウの作品について、ピアノのためのソナチネが子ども達にもよく演奏され、フルートの作品もよく聴かれ手居るが、その他に関してはあまりよく知られていないのが実情である。様々な意味において、東京での『ルル』上演は、これまでの音楽史における認識に、新たな一石を投じるに違いない。(6月4日 東京文化会館大ホール)
「ショパン」8月号(2005) 131ページ
![]() 音楽舞踊新聞No.2666(平成17年6月21日号)掲載記事
音楽舞踊新聞No.2666(平成17年6月21日号)掲載記事
親しみある美しい旋律連なる「魔笛」と原典同じオペラ
~167年ぶり本格上演、クーラウの「ルル」~
小崎 智華
デンマークで活躍した作曲家、フリードリヒ・クーラウ(1786年~1832年)の、ジングシュピール形式のオペラ「ルル」が、6月4日東京文化会館で上演された。このオペラの本格的上演は、167年ぶりという。
クーラウは、初歩のピアノ曲,或いはフルート作品で知られている。ドイツ生まれ、コペンハーゲンに移り、同地の宮廷作曲家になった。オペラ数曲や多くの室内楽曲、ピアノ曲、フルート曲を書いた。現在では、デンマークの国民的作曲家の一人に挙げられている。
さて、今回上演されたオペラ「ルル」は『〈魔笛〉よりも〈魔笛〉ママ』とプログラムにも書かれているように、原典はリーベスキントの「ルル、又は魔法の笛」(1791)と原典は同じ。
「ルル」はこれを基にギュンテルベアが台本にした。クーラウとしては、前作の「魔法の竪琴」の、“魔法オペラ”での、音楽は人間の精神に優るという、当時好まれたオペラの主題に加えて、好みのフルートを使うことの出来る題材として打って付けと言えた。「魔笛」台本作者はシカネーダーとされるが(これには異論もある)、主な源泉はアベ・ジャン・テラソンの「セトス」(1731年出版)という神秘物語で、この中にリーベスキントのこの物語が多く見出せ、また、「ルル、又は魔法の笛」と同名の童話集(ヴィーラント「ジンニスタン」)にも取り入れられている。
このクーラウに魅せられたのが、フルーティストの石原利矩氏、リサイタルでクーラウを取り上げたが、プログラムノートに書く資料がなく、デンマークにまで出掛けて調べるうちに、その魅力に引かれ、クーラウ協会を立ち上げ、このオペラの演奏会形式上演を経て、この日、本格上演となった。満員の会場に感慨無量のものがあったろう。
物語は、光の妖精ペリフェリーメが治める森で虎を退治した若者、コラッサン王国の王子ルルが、妖精の娘シディが岩山に住むディルフェングに捕らわれていると聞き、救出に向かう。妖精から授けられたのは、魔法の指輪と魔法の笛、ディルフェングは、シディの心を我がものとし、精霊界を支配する薔薇の蕾を開かせようととしていた。ルルは魔法の指輪の力で老人に姿を変え、ディルフェングに立ち向かう。シディとディルフェングの婚礼の場で笛を吹き、指輪を投げつけ大団円。ペリフェリーメはシディとルルを神殿の祭壇に迎え、愛の勝利を讃える。
4時間の作品を、正味3時間10分にまとめた。
あらすじを読んだだけでも「魔笛」と似通っていることが分かる。「魔笛」の夜の女王(悪)は光の妖精(善)であり、ディルフェング(悪)は「魔笛」では高僧ザラストロ(善)。ルルが救出に向かう際に授けられたのが笛と指輪で、「魔笛」では笛と鈴。面白いのはディルフェングが大団円で、シディと救援のルルに怒り、嵐を呼び寄せ雷を鳴らすところがあるが、これは「魔笛」の女王そのものだ。
物語の展開からすると「魔笛」にはどんでん返しという意表をつく着想があり、また、道徳的な思想が色濃いとする学者は哲学的思想を持つ一種の象徴劇と見る。そうでありながらあまりにも童話的世界が繰り広げられているのだ。ジングシュピールも効果的に使われ、モーツァルトの天才ぶりは、その音楽も含めて今もって新鮮なのである。
「ルル」からはウエーバーやロッシーニ、モーツァルトなどいろいろな音楽が聴こえてくる。そういった点では、ごく普通のオペラ作品といえよう。しかしその旋律は、全編を通して美しく連なり、親しみやすさを多く持ち、そしてそれは今もなお生き生きしている。また、1824年にコペンハーゲンで初演されたその当時の音楽状況が反映されている一方で、その後のデンマーク音楽に影響を与えた偉大な作品であることを、認識させる。
ペリフェリーメの夏木マリはセリフだけだが、女優らしい達者な語り口で、一際引き付けた。ルルは福井敬。コロラトゥーラといった華々しい歌唱こそないが、ルル役とともに難役のシディに澤畑恵美。両人の活躍は目覚ましかったが、ディルフェングの松本進、その息子バルカの久岡昇の歌唱、演技はすばらしかった。バルカの惚けた『ない、ない、ない』の歌は、特に持ち味を生かした。ヴェラの高橋薫子も好演。
演出は十川稔。分かりやすい舞台構成。一部に不満はあるが、大勢に影響がないので省く。衣裳は佐野利江。古いロシア風あり、アラビアン・ナイト話風あり、ペリフェリーメの白い豪華ドレスが照明に浮き上がり、燦然と輝いていた。上演は日本語。歌唱も含め言葉がよく聞き取れないところもあり、その点は残念。音楽総監督にゴルム・ブスク(クーラウ研究家)。
何よりも拍手を送りたいのは、音楽をよく読み込み、指揮もした石原利矩。フルートソロはトーケ・ルン・クリスチャンセン。東京ニューシティ管弦楽団、東京合唱協会、谷桃子バレエ団、この総合力で、価値ある上演を成し遂げた。
![]() 静岡新聞 6月13日夕刊
静岡新聞 6月13日夕刊
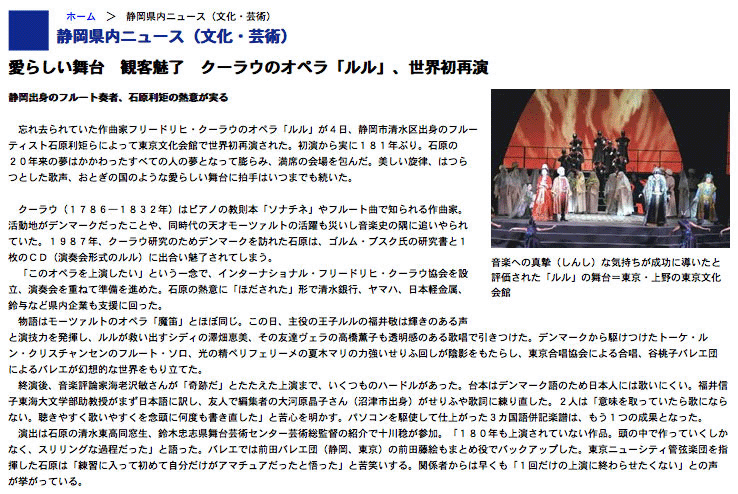 |
![]() 毎日新聞2005年3月10日夕刊掲載記事
毎日新聞2005年3月10日夕刊掲載記事
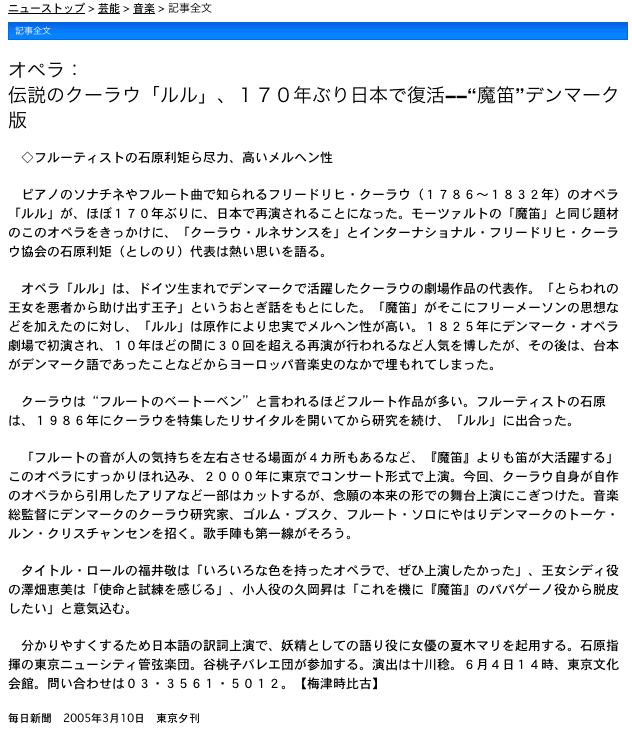 |