いくつもの魔笛、そしてもう一つの魔笛 (海老澤 敏)
オペラ『ルル』演奏会形式プログラムより
2000年3月26日
東京オペラシティコンサートホール
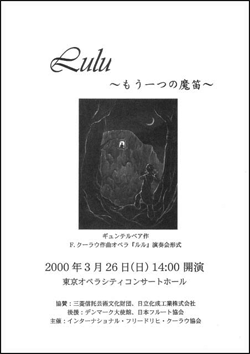 |
いくつもの魔笛、そしてもう一つの魔笛
海老澤 敏
《魔笛》。この不思議なともいうべき日本語は、おそらくはモーツァルトの最後の年の名作歌劇を名指す以外には使われることがないものであろう。まさに不思議な力を持って鳴り響く笛という理解の上に、この言葉は、明治このかた、この不世出の古典派音楽家のドイツ語歌劇の訳語として人口に膾炙してきた。明治時代には、《霊笛》という訳語も試みられたが、こちらのほうはいつしか忘れられてしまったことも思い出される。 そのモーツァルトの《魔笛》(K620)は、彼の生涯に亘って書かれたおよそ20曲ものオペラの中でも、およそ特別な作品として、作曲者の死後200年を越える長大な年月を生きつづけてきた。もちろん、彼モーツァルトのいくつかのイタリア語オペラも、別の意味で同じような永遠のレパートリーをオペラ史に提供してくれていることは否定すべくもない。たとえば、《ドン・ジョヴァンニ》(K527)がそれで、この作品もまた、二世紀間、後世のさまざまな解釈の試みの恰好の対象でありつづけてきた。 だが、《魔笛》ほど、その素材自体と音楽そのものが、後世の観客、聴衆の解釈学の対象という、いささか恣意的なアプローチではない形で観られ、聴かれてきたモーツァルト・オペラはほかにはないのではなかろうか。 いささかむずかしい論議から入ってしまったが、砕いて言えば次のようになるだろう。モーツァルトの《魔笛》が、いわゆる〈フェアリー・テイル〉、すなわち〈御伽話〉的な内容を持っている点は、その筋書からして当然で、そうした了解の下に、初演がおこなわれた時点以降、ドイツ全土でもてはやされて行ったことは疑いがない。悪を象徴する夜の女王とそれに対決する善の代表ザラストロという構図、あるいは純真な乙女パミーナと誠実な王子タミーノの真摯な愛、そしてパパゲーノの滑稽な道化芝居。 しかし、そうした御伽オペラ《魔笛》の中には、初めから、つまり台本作者シカネーダーと作曲家モーツァルトのオペラ作りの発端から、別の要素、異なった側面が加えられていたことも確かであった。すなわち、後世が一旦は忘れたのか、意識的に避けたのかはいざ知らず、その面を無視さえしたと思われるフリーメイスン結社思想の表現であった。シカネーダー=モーツァルトが、この点を明確に意識しつつ、このオペラを作ったことは、初演台本の扉絵の、一見不思議な視覚的提示からも知られる。そして、このフリーメイスン的方向と内容は、なかんずく、20世紀に入ってから、演出家、聴衆、そして文人や哲学者をはじめとする論者、さらには研究者によって追究されてきたのであった。 とりわけ20世紀後半という今、まさに去りゆきつつある一つの時期には、ジャック・シャイエーの著書『魔笛─メイスン・オペラ』(1968年)に代表されるような捉え方が中心となったのである。 振子は一方に振れれば、必ず逆の方向に動く。この現象が、今、ふたたび起こりつつある。そして、それも、ただ単なる揺り戻しの形ではなく。それが意味するところをかいつまんでお話ししてみよう。 それは御伽話的な《魔笛》理解の復権とも言うべきだろうか。近年の演劇史的、そして音楽史的研究は、モーツァルトの時代についても、この作曲家の個人史的、つまり周囲から切り離された孤絶した一人の人間の伝記的アプローチに留まらず、周囲の資料の発掘や解読によって、当時の社会史的状況をつまびらかにする方向をとってからすでに久しい。 モーツァルトが《魔笛》を作曲し、上演した、1791年をめぐる当時のドイツ語オペラのヴィーンにおける状況もまた多くの研究家によって究明されつつある。たしかにモーツァルトの《魔笛》は、作曲者の空前絶後とも言うべき音楽的超絶性によって、時代を超えて生きのび、オペラ史、音楽史、文化史の中で、最高峰の一つを形づくっている。 それはしかし、むしろ、極端に例外的な現象なのだ。凡百の、普通のオペラ作品は、凡百の、凡庸な作曲家によって生産され、観衆によって消費され、そのあと御蔵入りして消え去って行く。そうした作品たちが、研究家たちによって踏査され、発見され、そして再評価される。こうした昨今の趨勢の中で、シカネーダー=モーツァルトのジングシュピールの制作状況は、次第に明らかにされつつあるのが現状なのだ。ここ10年、20年という時期的範囲で、今までモーツァルトとの関係でしか問題にされることのなかったエマーヌエル・シカネーダーの活動が、彼を中心とする演劇一座の活動、あるいはヴィーンにおける演劇・オペラ活動、さらにはドイツ語圏における舞台芸術活動といった視座で新たに評価されつつある。 それはモーツァルトの、とりわけ晩年のオペラ活動を、従来の個人史的、伝記的観点を超えて、あらためて定位することになる。シカネーダー=モーツァルトの《魔笛》に先立つこと四か月ほど前に、ヴィーンではヨーアヒム・ペリネットとヴェンツェル・ミュラーによる作詞・作曲で、《ファゴット吹きのカスパルまたは魔法のチター》なる三幕物のジングシュピールが上演されている。シカネーダーの拠点だったヴィーデン劇場とはライバル関係にあったレーオポルトシュタット劇場で舞台にかけられたこのジングシュピールは、その題材の共通性からして、私たちをさらに、シカネーダーやペリネットがその台本の手本としたアウグスト・ヤーコプ・リーベスキントの《ルルまたは魔法の笛》の世界へと、そしてまたそのリーベスキントの御伽話を収録したクリストフ・マルティーン・ヴィーラントのアンソロジー『ジンニスタンまたは妖精・魔鬼譚精選』(全3巻)の世界へと導いてくれるのだ。 こうした遡及、関係の広がりの中で、ここ二、三年、新聞雑誌を賑わせたシカネーダー・オペラ《賢者の石》(1790年)、そして《親切な托鉢僧》(1791年)に関する再発見、新発見のニュースが登場する。両者は昔からある程度知られていない訳ではなかったし、とりわけ《賢者の石》へのモーツァルトの関与(K625=592a)は知る人ぞ知るものであった。 しかしながら、これらの作品が、いずれもヴィーラントの『ジンニスタン』の〈御伽話〉作品の圏内にあることも、またきわめて重要であろう。この二つの作品に対するモーツァルトの関係は、彼ひとりの創作になり、現在に至るまで、すでに述べたような孤高の高みにありつづける《魔笛》とは異なったものであり、彼はそこではシカネーダ一座の座員たちに加わっての共作者であるにすぎない。だが、その彼らとの共同作業の中で、モーツァルトは彼らに同化しつつ、そして協作しつつ、そのジングシュピール的な,喜歌劇的な様式を共有し、同時に彼自身のユニークな、一回的な作品である《魔笛》の独自様式への連関も図っていることもまことに奇跡的な芸術的行為と言うべきであろう。 この〈シカネーダー=モーツァルト1791年〉の奇跡はまた、モーツァルトの死後、シカネーダーのたとえばヴィーンばかりでなく、さらに広いドイツ語圏内での、一座の活動へと継承されていく。シカネーダーが重要視したのは、前述の〈ヴィーラント御伽話〉の数々であった。ちなみにこうした試みは、モーツァルトの生前にすでにギーゼケ=ヴラニッキーの《妖精の王オーベロン》(1789年)によって始められているが、ポスト・モーツァルトの時代に入っても、1790年代にはドイツ語圏の各都市で、《魔笛》はもとより《賢者の石》などの上演活動によって続けられて行く。 1801年に開場したアン・デア・ヴィーン劇場を本拠とするシカネーダー一座の活動もまた、こうした流れを推し進めたのであった。そして、それが、やがて、1820年代初めのカール・マリーア・フォン・ヴェーバーによるロマン的オペラ《魔弾の射手》(1821年)へとつながって行くのもまた確かなのだ。 そして〈もう一つの魔笛〉、すなわちフリードリヒ・クーラウの《ルルまたは魔法の笛》(1824年)が立ち現れる。この作品、今日、日本で初めて紹介されるクーラウの代表的舞台作品が、《魔弾の射手》と、同じヴェーバーの〈ヴィーラント御伽オペラ〉の名品《オーベロン》(1826年)の間に試みられているのも注目に値しよう。 この〈もう一つの魔笛〉について私がここで喋々するのは差し控えたいが、このオペラが上述の歴史的位置、そして、本プログラムの解説が明らかにするだろう音楽的内容、そしてそのいろいろな意味で親しみ深い響きによって、今まで深く沈んでいた忘却の渕から掬い上げられ、完全に復活しつつあるのを心からよろこびたいと思う。 |
インターナショナル・フリードリヒ・クーラウ協会